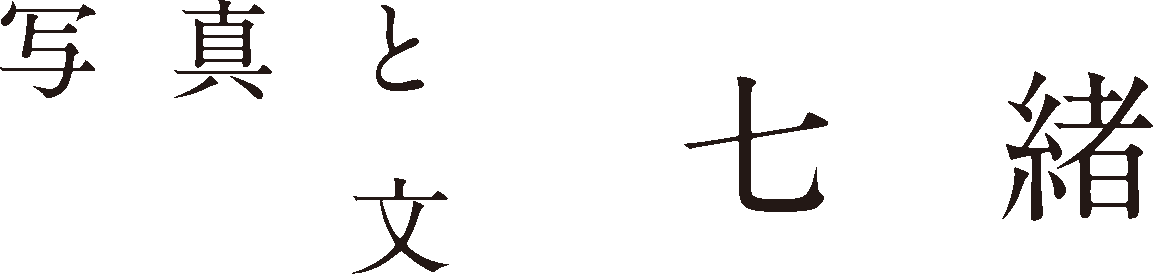5月5日は私にとってはじまりの月です。
9年前の今日。友人を撮った所から今のキャリアは始まりました。当時は地方公務員として働いていたと思うと、不思議な気持ち。遠い昔のような、でもその時の私は今とたしかにつながっている。
今日はこの9年間、とりわけここ2〜3年の心境の変化について書き残したいと思います。上を目指し続けていた9年前。そして目の前を大事に積み重ねたい今。
写真をはじめた当初は、認められたい気持ちがかなり強かったです。私が有名になりたい、私が一番になりたい。それは学校教育や会社組織など、いつだって上を目指すことが正解という価値観で生きてきたのも大きいと思います。
公務員を辞め、ほんっっとうにコネもツテもない中、フォトグラファー/ライターとして生き延びていくには、そのマインドは必要不可欠でした。深夜まで続くアシスタント、毎年の個展、出版…がむしゃらに進むガソリンでもありました。
でも走り続けて5年ほど経った時、じわじわと気づいたのです。
「わたし、いつまで走り続けないといけないの?」
そんなモヤモヤを軽やかに晴らしてくれる変化が、2020年以降立て続けに起こり、本当に生きやすくなりました。植物療法、前田敦子の”月月”、出産。どれも欠かせないエッセンスなので、一つずつ。
まず植物療法に出会ったこと。10年前から冷えとりで体を整える中で、セルフケアの力に気づいていました。撮影という一発勝負の場で良いパフォーマンスを発揮するのに良さそう!と足を踏み入れたら、美しくやさしい世界がそこにありました。
精油やハーブを学び実践することで、不調はみるみるうちによくなったし「何者かにならないと」馬車馬のように走り続けていた私がそうではないあり方に触れて、肩の力がすとんと抜けました。温泉のように心地よいのに、物事もちゃんとうまくいく世界。
「今のわたしで100点満点」そう気づけたことで、心身ともに、本当に生きやすくなりました。その気付きが好評配信中のラジオ「セルフケアジャーニー」や毎日のハーブのブレンドにつながっています。

植物療法の学びが一段落した2021年1月。前田敦子さんを毎月撮り下ろすプロジェクト「前田敦子の”月月”」をはじめました。
一人の女性に向き合い続ける時の重みは、今まで関わってきたどの仕事・作品とも異なるもの。被写体の人生に深く関わりながら、うれしい時も悔しいときも生きる姿を残すこと。その奥深さ、難しさ、喜び。
印象的だった出来事があります。それは2022年8月に渋谷PARCOで開催した写真展。写真に加え、音、香りも演出したことで、雑然とした渋谷の地下が調和的な空間に。涙を流したり、自身のことを打ち明けてくれる人がたくさんいました。
この経験を境に、空間づくりに興味を抱くようになっていきました。心地よい場を作ることで、人が心を開き、本来の私に戻っていく。撮影やインタビューでアプローチしていたことが、五感に響かせながらできる。その気づきが鎌倉の「光と緑の家」へとつながっていきます。

時を同じく出産。仕事や表現の大元である暮らしに目を向ける時間がぐんと増えました。何を成し遂げるにしても、成し遂げないにしても、今、目の前にある暮らしと体からすべての表現がはじまる。その暮らしや体は、心地よい方がいいに決まってる。
3つの出会いを経て、私は大きく変わりました。という深まっていったという方がしっくり来るかもしれません。
植物療法から、自然と調和し心身を整える心地よさを。
前田敦子の”月月”から、人と向き合う奥深さと空間の力を。
出産から、暮らしへのまなざしを。
そして春、鎌倉に引っ越したことで、すべてがまあるく調和していく感覚があります。


これからは、自然と調和する暮らしを真ん中に据えて、光と緑に満ちるこの家を起点に、みなさんが心地よく前を向くお手伝いをしていきたい。写真と文をベースに植物の力も取り入れながら。それはIt’s me!だし、ラジオだし、もちろんクライアントワークも。前を向く、というのがポイントです。
振り返ってみると、独立当初、女の子を撮りまくっていた頃と、軸は変わらないのです。当時は撮影で女の子が自分に目を向け、好きになれるきっかけになれたら…と思っていた。歳を重ねるにつれてそのアプローチの数が増えていったのでしょう。
この道がどこにつながっているかはわからない。でも今の私が進みたい道であることはたしか。

(今朝、鎌倉の光の緑の家にて)
実は毎年5月5日にブログを書いています。初期の方は小っ恥ずかしいアツさです(笑)
はじまりの日「🔗ガールズフォト#2」
1年目のブログ「🔗ガールズフォトグラファー・1年目の軌跡」
2年目「🔗フォトグラファー・2年目の軌跡」
3年目「🔗フォトグラファー・3年目の軌跡」
4年目「🔗フォトサービスIt’s me!リニューアルオープンしました」
5年目「🔗家族と一緒にいたいから引越しました」
6年目以降は出産後のバタバタで書いていなかった。でも節目の日に書き残すってやっぱりいいですね。最後までお読みいただき、ありがとうございました!